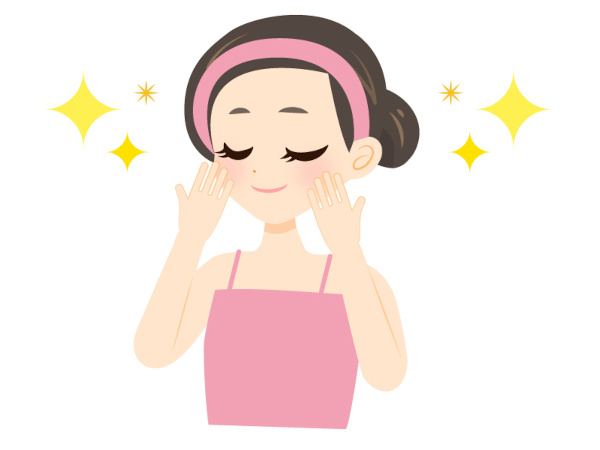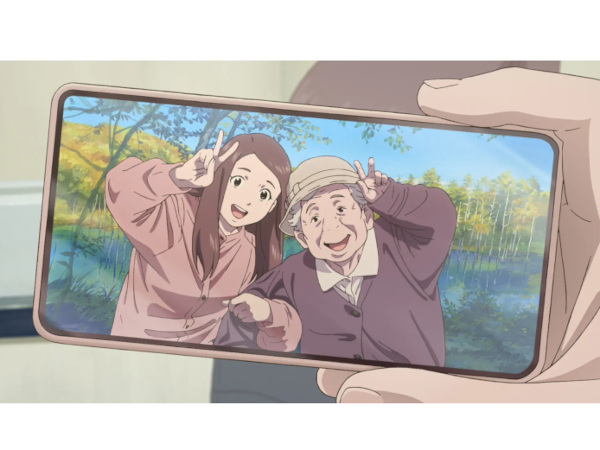- 健康管理!教えて!!2025/06/02 22:44
「内臓感覚」の仕組みとは? 臓器に分布している受容器で刺激を感じ取り痛みなどの信号を発生

空腹やのどの乾き、吐き気、尿意や便意などの様々な感覚は、内臓から発生した信号によってもたらされています。これらの感覚や内臓痛をまとめて「内臓感覚」と呼びます。では、内臓感覚はどのような仕組みで起こるのでしょうか。
内臓感覚は、臓器に分布している受容器で感じ取っています。例えば、内臓を動かす平滑筋の中や、心臓の壁を作る心筋、内臓の粘膜などにある受容器が発痛物質の発生を感知したり、臓器の動きによって圧力を受けたりすることでもたらされます。内臓では、皮膚よりも神経が少ないため、どこが刺激されているかという感覚はあまりなく、消化管にメスを入れたとしても痛覚は生じません。
内臓痛は、皮膚の痛みとは違い、非常に限局した障害では起こらず、臓器が広範囲に損傷を受けた場合に感じられます。内臓痛は、内臓平滑筋が痙攣を起こして強く収縮・伸展されたとき、また、内臓に酸素や栄養素を送る血管が循環不全を起こしたときに生じます。
痛みは神経を通って脊髄から脳へと伝えられますが、その際、皮膚の特定の部分に不快感や痛みを感じることを「関連痛」といいます。例えば、肝臓疾患の時に右肩、心臓疾患の時に左上腕に痛みや不快感を感じることがあります。これは、脊髄で内臓からの感覚神経と皮膚からの神経が集まり、大脳皮質へ伝達される際、脊髄において内臓神経痛を皮膚からの痛覚刺激として認識するからです。そのため関連痛は、内臓疾患の診断に非常に重要とされています。
内臓感覚の反応には、脳に届いて意識できる感覚をもたらすものと、脳を介さずに脊髄や脳幹で臓器に戻る信号を発生させる(反射を起こす)ものとがあります。体に悪い食べ物を食べたときなど、強い吐き気が起きて食べ物を戻すことは反射による反応です。食べ物に含まれる有害な物質が胃の筋肉にある受容体を刺激し、発生した信号が脳の延髄にある嘔吐中枢に伝わるためです。嘔吐中枢からは胃の筋肉や横隔膜、腹部の筋肉を動かす信号が出て、胃の内容物を食道に押し戻す動きが起きます。これは、体が備えている緊急避難の方法の1つで、体内に有毒物が入ったときにできるだけ早く排出するために備わった機能なのです。(監修:健康管理士一般指導員)