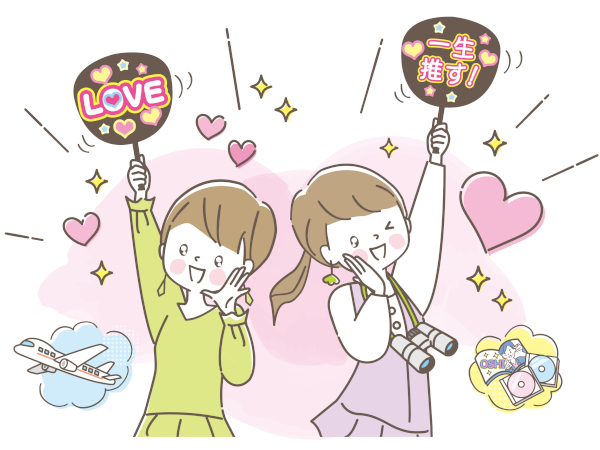- 健康管理!教えて!!2025/01/08 22:32
歩幅を広げると認知症の予防につながる? 股関節と脳機能の深い関わり

股関節は、「歩く」「座る」などの移動動作や、「立つ」などの体重支持動作に必要不可欠な関節で、日常生活において非常に重要な役割を果たしています。そして、あまり知られていませんが、実は股関節は脳の機能と大きな関わりがあるといわれています。その指標となるのが「歩幅」です。
歩幅は体のバランスや安定性に関連しており、様々な場面に合わせてコントロールされています。例えば、平らな大きい道路では広い歩幅で歩けたり、デコボコ道や整備されていない道路では転ばないよう歩幅が狭くなったり、濡れている道路では滑らないよう歩幅が狭くなったりします。また、高齢者の場合は歩く際に安定性を確保しようと、歩幅を広げずに狭めて歩く傾向があります。これは、無意識のうちに転倒やバランスを崩すリスクを減らしているためです。
しかし、股関節が硬くなり、日常的に歩幅が狭くなると、歩くスピードが落ちるだけではなく脳機能を低下させることにもつながります。歩幅の調節には脳の多くの部分が関与しており、歩幅が狭い人は、広い人に比べて認知機能が衰えやすいといわれています。それは、歩幅を調節しているのは主に大脳皮質であり、認知機能に関係する脳の部分と重なっているためと考えられています。
そこで、おすすめしたいのが歩幅を意識して歩くことです。これによって、普段使っていない筋肉が意識的に使われ、脳内で新たな神経回路が構築されたり、脳の血流が向上し、脳の活性化も期待できるといわれています。近年では、歩幅を広げることが認知症予防や治療に役立つ可能性があると考えられています。
歩幅は歩く時に開く右足のつま先から左足のつま先までの幅を指し、理想の歩幅(広い歩幅)は65cm以上といわれています。わかりやすい例えでは横断歩道の白線があります。白線の幅は約45cmであり、足のサイズを25cmとすると、白線を踏まずに跨げれば一歩の歩幅は70cmとなります。このように、白線を踏まないで跨げるかが歩幅の広さの簡単な目安になります。
歩幅を無理なく広くするコツは“腕を後ろに振る”ことです。腕を前に振ると体が前傾し猫背になりやすく、逆に後ろに振ると背筋が伸び視線が上がり歩幅が広がりやすくなります。まずは、今の歩幅から5cm広げることを意識して歩いてみましょう。(監修:健康管理士一般指導員)