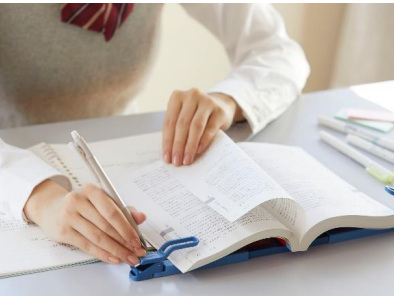- 健康管理!教えて!!2025/08/21 23:12
T細胞を教育する「胸腺」とは? 免疫系で重要な役割を担い10代前後をピークに発達

リンパ球の一種であるT細胞は、「胸腺(Thymus)」で作られるため頭文字を取って「T細胞」と名づけられました。T細胞は、他の免疫細胞の働きを調節する司令塔として機能する「ヘルパーT細胞」、ウイルス感染細胞やがん細胞を直接攻撃する強い威力を持った「キラーT細胞」、ヘルパーT細胞やキラーT細胞の働きを制御する「制御性T細胞」があります。
胸腺は、胸骨の裏側、心臓の上にある臓器で、T細胞を教育し、成熟させる役割を担っています。生後すぐは10~15g程度ですが、思春期には30~40gほどの大きさになり、成人してからは徐々に小さくなっていきます。胸腺は左右の小葉から構成され、皮質と呼ばれる外側の部分と髄質と呼ばれる中心部分に分かれています。
ほとんどの免疫細胞は骨髄で生まれ骨髄で成長するのに対し、T細胞は骨髄で生まれ、胸腺の皮質に運ばれて厳正な教育を受け成長し、血液やリンパ液に送られます。胸腺でのT細胞の教育は、骨髄で行われるB細胞の教育よりも厳格です。B細胞は2つの試験でしたが、T細胞は自己を認識し、自己を攻撃しないためにさらにもう1つの卒業条件が組み込まれています。前駆T細胞が、未熟(ナイーブ)T細胞として卒業するためには、「適切で多様な抗原受容体を作れること」、「適度に自己と反応できること」、「自己に強く反応しすぎないこと」の3つの条件をクリアする必要があります。
免疫系において重要な役割を果たす胸腺は10代前後をピークに発達し、その後は脂肪となって徐々に退化していきます。加齢にともなって免疫力が低下し、高齢者は感染症に対する抵抗力が低下します。これは高齢者の健康、疾患のリスクを考える上で重要な課題になっています。マウスを用いた研究では、免疫力の低下に最も顕著なのはT細胞の機能低下が大きく関係していることが明らかになっています。
また、胸腺で「卒業」したばかりの未熟(ナイーブ)T細胞は、血液循環系に入り、多くは全身のリンパ節や脾臓に分布します。これらの場所でT細胞は成熟し、樹状細胞が運んできた異物(抗原)と出会い、情報を受け取って分化・増殖します。しかし、加齢とともに胸腺が萎縮するため、未熟(ナイーブ)T細胞の産生量が減少します。その結果、体内のT細胞の総量を維持するように働くため、これまでに獲得した異物の情報を記憶したT細胞(メモリーT細胞)が増殖します。この仕組みによって過去に感染した病原体に対しては免疫システムがうまく働いて対処できますが、新型インフルエンザなどの未知のウイルスに対しては、免疫システムがうまく機能せず、感染リスクが高まると考えられています。(監修:健康管理士一般指導員)