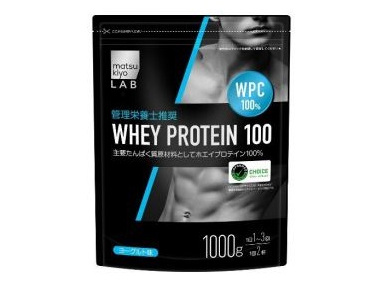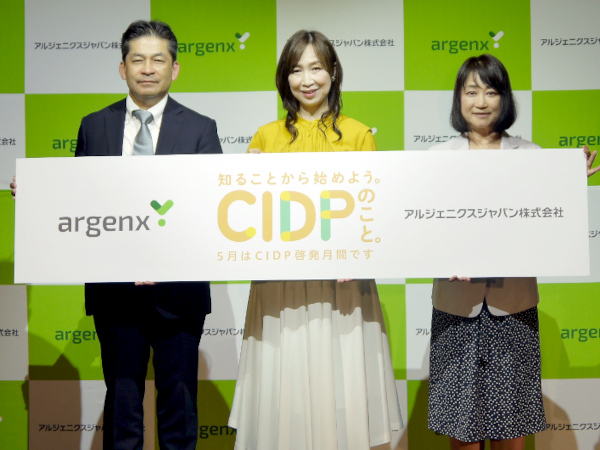- Health&Medical2025/11/18 19:34
大塚製薬、認知症の人の気持ちに寄り添う情報サイト「認知症 困りごとナビ」を展開、認知症に向き合う家族や介護者の支えに

日本が超高齢社会に突入する中、認知症は本人のみならず、家族をはじめとする介護者の人々にとっても深刻な課題となっている。大塚製薬は、認知症に対する取り組みや啓発活動に注力しており、その一環として、認知症の人の気持ちに寄り添う情報サイト「認知症 困りごとナビ~認知症の方の気持ちを知る~」を展開している。今回、同サイトを監修する医師の近畿大学医学部 精神神経科学教室 主任教授 橋本衛先生と、家族を支援する立場の新潟青陵大学 福祉心理子ども学部 准教授の野口代先生に、それぞれの視点から“日常の困りごと”や同サイトの活用法について聞いた。
「認知症 困りごとナビ~認知症の方の気持ちを知る~」は、認知症の人との日常で起こりうる“困った”場面を、わかりやすく解説する情報サイト。一般的に、認知症の症状といえば、もの忘れに代表される「認知機能障害」が知られている。しかし実際には、「最近怒りっぽくなった」「夜中に徘徊する」「物を盗られたと訴える」など、家族にとって“困った”と感じてしまうような行動も少なくない。これらは、認知症にともなう行動・心理症状(BPSD)である可能性があるという。同サイトでは、こうした場面を含む全16種類の“困りごと”を紹介し、認知症の人の気持ちに寄り添いながら、日々をともに過ごすためのヒントを届けている。
日本では現在、認知症の症状が悪化したり、認知症にともなう行動・心理症状(BPSD)が現れてから医療機関を受診するケースが散見され、結果として本人だけでなく、家族や介護者の負担が大きくなっている状況が課題となっている。総務省の「就業構造基本調査」(平成24年、29年、令和4年)によると、介護を理由に離職する人は年間約10.6万人、また介護と仕事を両立している人は約364.6万人にのぼるとされており、社会全体での理解と対応が求められている。こうした状況を少しでも改善し、認知症と向き合う家族や介護者が、正しい知識とケアの手がかりを得られ、認知症の初期段階で医師に相談できる人が増えるよう、同サイトを開設したという。

サイトの監修を手掛けた橋本先生は、「このサイトは、認知症の人と暮らす中で家族が『困った』と感じやすい場面を取り上げ、その背景にある気持ちを理解しながらより良い接し方を考えるための情報を提供している。現在、代表的な16の事例を専門的に解説し、対応のヒントを示している。また、日常の行動を整理し医師や支援者に伝える『相談シート』を用意しており、受診や地域支援につながるきっかけとして活用できる。信頼できる情報源として、家族や介護者の安心につながることを目指している」と説明する。
野口先生は、「同サイトは、認知症の人の行動に戸惑う家族が、接し方を見直すきっかけとして役立ててもらえるように作られた。日常生活でできないことが増えたり、意欲が低下して行動を避けるようになると、家族は『進行を防ぎたい』と考え、無理にやらせてしまうことがある。しかし、その対応がかえって本人の不安やいら立ちを強め、関係を悪化させることもある。同サイトでは、その背景を理解し、安心できる環境や関わり方へ切り替える視点を紹介している。会員登録や費用は不要で、気軽に利用できるのも特徴。『ちょっと困った』と思ったときに開けば、すぐに役立つヒントが見つかるはず」と、サイトの特徴について紹介した。

「医師や専門医に相談していいこと」を気づけない家族に、どのような気づきを届けたいかを聞くと、野口先生は、「家族の中には、『年のせいだから』『まだ大丈夫』と受診を先延ばしにしてしまう人もいる。また、認知症だと認めたくない気持ちや『もし認知症だったら』という不安から、相談を控えてしまうケースも少なくない。その結果、一人で抱え込み、負担や不安がさらに大きくなることもある。同サイトは、『こんな時は医師や専門家に相談してもよい』という視点を持ってもらうことを大切にしている。事例を知ることで『自分だけではない』と気づき、相談や受診の一歩を踏み出すきっかけになることを期待している」と述べていた。
認知症について悩みを抱えている家族や介護者に、サイトをどのように役立ててほしいかを聞くと、橋本先生は、「同サイトは、家族が直面する“困った行動”を理解し、接し方を考えるきっかけとなる場。『いつもと違う様子』に戸惑う家族は多いが、その背景には本人の不安や気持ちが隠れている。大切なのは、単に向き合い方を知ることではなく、『なぜその行動が起きているのか』を理解する視点。この考え方を持つことで、特定の症状への対応にとどまらず、さまざまな場面に応用できるようになる。こうした工夫が、認知症の人との関係を良くし、家族にとっても安心につながると考えている」と話す。
野口先生は、「『これまでと少し様子が違う』と感じたら、早めにサイトをのぞいてみてほしい。例えば、『入浴や食事を嫌がる』『夜中に何度も起きる』などの変化は、本人の不安の表す。そのままにすると家族の負担大きくなる可能性がある。同サイトでは、こうした行動の背景や具体的な対応の工夫を紹介している。時間や場所を変えるだけで落ち着く場合もあり、少しの工夫で介護の負担を和らげると考えられる。認知症の人と相談し、本人の意思に寄り添いながら向き合うことで、本人も安心し、家族もより穏やかな気持ちで日々を過ごせるようになる」とアドバイスしてくれた。
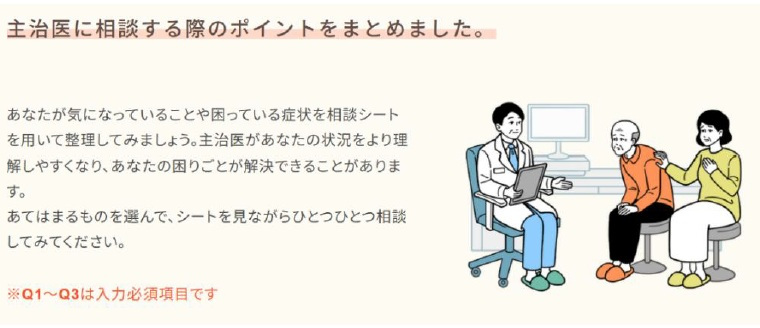
サイト内で提供している「相談シート」の活用法について聞くと、橋本先生は、「『相談シート』は、家族が日常で気づいた行動を整理し、診療時に医師へ正しく伝えるために役立ててもらいたいツール。ちょっとした気づきも受診の際には忘れてしまいがちだが、書き留めておけば大切な情報を漏らさず伝えられる。箇条書きにまとめることで『これも認知症の症状かもしれない』と気づくきっかけにもなり、診療を円滑に進める助けとなる」とのこと。また、野口先生は、「『相談シート』は、『どう話せばよいか分からない』という家族の不安を和らげる役割がある。小さな変化や困りごとを記録しておけば内容が整理され、受診もスムーズになる。本人の前では言いにくいことも、紙に書いて医師に渡せば確実に伝えられるし、気になる場合は受診前に受付に預けておくこともできる。こうした工夫によって相談のハードルが下がり、支援につながりやすくなる」と教えてくれた。
最後に橋本先生は、「認知症の人の『困った行動』の背景には、本人の不安や戸惑いが隠れていることがある。認知症にともなう行動・心理症状(BPSD)を正しく理解し、その気持ちに寄り添うことで接し方が変わり、家族の負担も軽減される。このサイトは、そうした視点をもつための手助けとなることを目指している。さらに、介護者が孤立せず、地域の支援や医療機関とつながりながら、安心して介護に取り組めるよう、サイトを活用してもらればと思う」と、同サイトを通じて認知症に向き合う家族や介護者をケアし、医療機関につないでいくと訴えた。
野口先生は、「このサイトは、困りごとを整理し対応の工夫を示すだけでなく、『介護は一人で抱え込むものではない』というメッセージを伝える役割も担っている。困りごとの多くは病気によって自然に生じるもので、家族の責任ではない。誰にでもうまくいかないことはあるのだと安心し、気軽に相談してほしいと思っている。また、家族それぞれがサイトを見ることで共通の理解が生まれ、情報共有や話し合いのきっかけにもなる。そうした入り口として同サイトを活用することで、介護の負担を和らげ、本人と家族のより良い日常につながることを願っている」とメッセージを送ってくれた。
大塚製薬=https://www.otsuka.co.jp/
認知症 困りごとナビ~認知症の方の気持ちを知る~=https://www.smilenavigator.jp/ninchisyo/komarigoto-navi/