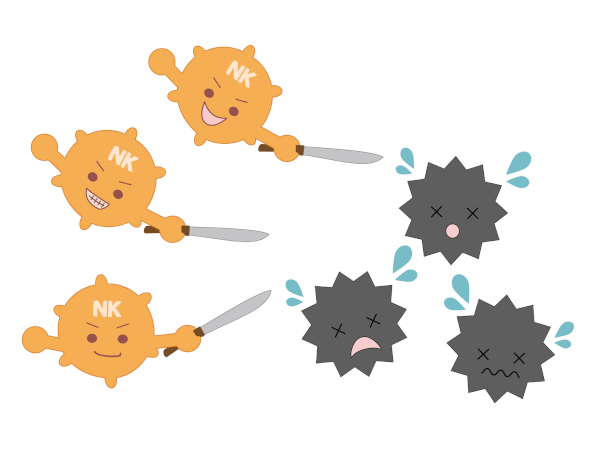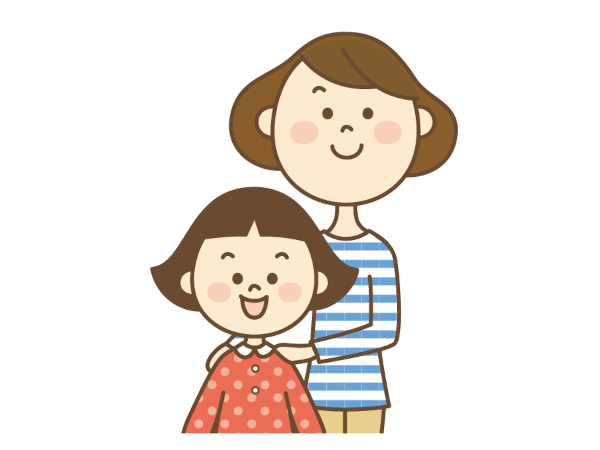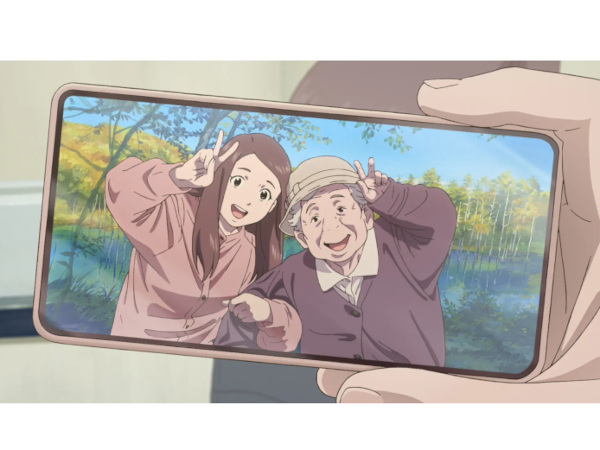- 健康管理!教えて!!2025/10/29 23:08
歯科疾患と生活習慣病の深い関係とは? 歯周病とメタボリックシンドロームは相互関係に

「歯磨きを怠けると歯周病になるのはわかるが、生活習慣病とは関係ない」と思っている人は多いと思います。しかし、歯科疾患の原因菌は、気道や血液を介して肺や全身へと回り、心臓病や動脈硬化、肺炎などの発症、糖尿病のコントロールへの悪影響、さらに早産や低体重児出産などの一因と関連していることが報告されています。そのため、虫歯や歯周病は、口の中だけでの病気ではなく、全身の健康と深く関わる病気でもあるのです。
特に、メタボリックシンドロームの判定基準である肥満と、日本人の50~60歳代の約半数が罹患しているといわれる歯周病は、相互に関係しあっていることがわかってきました。内臓脂肪型肥満では、炎症性の物質が分泌されやすく、それらが血管を通って口腔内に到達し、歯科疾患の進行を促進させると考えられています。逆に、歯科疾患にかかると、その原因菌が持つLPSという強力な炎症を誘発する毒素が、歯周組織から血管の中に侵入し、肥満と歯周病の治癒を遅らせるように働きます。さらに、体の中に炎症性物質が増えた状態が続くと、免疫システムのバランスが崩れ、抵抗力が低下することで健康を害するリスクが高まると考えられています。
また、内臓脂肪型肥満では、LDLコレステロールの増加傾向がみられますが、LPSが血管に侵入して内壁に付着して炎症を起こすと、そこにLDLコレステロールが沈着して瘤を作り、血管を痛めてしまいます。瘤が次第に大きくなると血流が阻害され、歯ぐきなどで微細な循環障害が生じます。さらに、LPSはリンパ球を刺激して炎症性物質を誘導し、血液中のコレステロールや中性脂肪を増加させる原因となってメタボリックシンドロームの1つである脂質異常症を引き起こします。
最近の調査では、メタボリックシンドロームの診断基準項目となる腹囲、脂質異常、高血圧、高血糖に該当する数が多いほど、歯周病をともなっていることが報告されているので、歯周治療と同時に血管を守る生活習慣の改善が必要になります。そして、各種代謝性疾患の進行をドミノ倒しに例えた図において、歯科はドミノの上流の生活習慣の改善と中流部分のメタボリックシンドロームの予防に介入することが可能であると考えられています。(監修:健康管理士一般指導員)