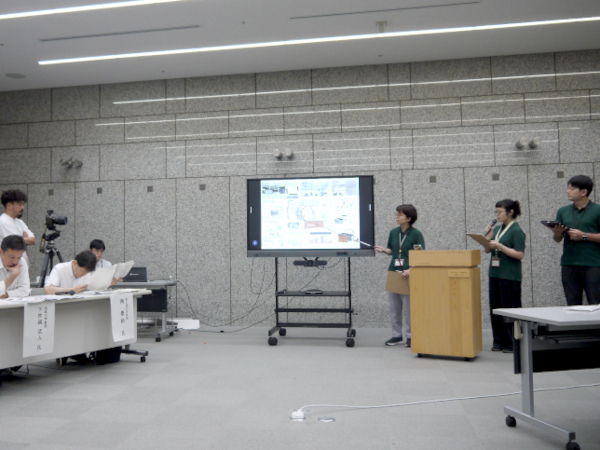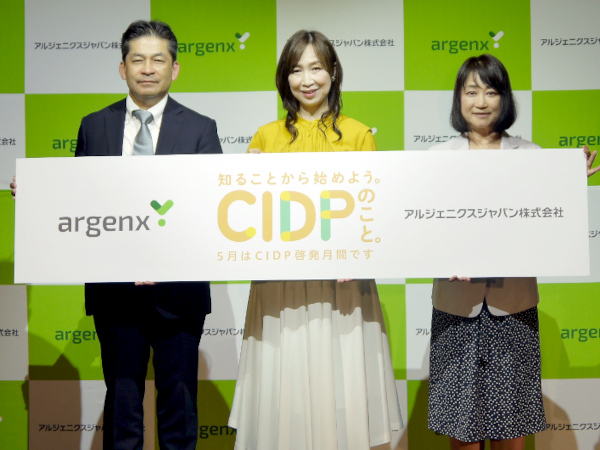- Study&Work2025/11/25 21:36
ReGACY Innovation Group、「Be Smart Tokyo 中間DemoDay 2025」を開催、採択事業者がプロジェクト概要や活動状況を報告

ReGACY Innovation Groupは、東京都が進めている「東京都スマートサービス実装促進プロジェクト(以下、Be Smart Tokyo)」の中間報告会「Be Smart Tokyo 中間DemoDay 2025」を11月12日に開催した。当日は、今年8月に新たに採択されたスタートアップ3社を含む採択事業者計8社が、各プロジェクトの概要や活動状況、今後の展開について発表した。また、注目プロジェクトとして、GATARI×三菱地所による「視覚障がい者を含む、誰もがアートを体験できる音声ガイドコンテンツ」および、Cuel×メリービズによる「女性のキャリア構築」についてトークセッションを実施した。

「東京都では、『スマート東京』の実現に向け、令和4年度から『Be Smart Tokyo』を実施している。このプロジェクトでは、都内全域をフィールドに、スタートアップと東京都が連携して、スマートサービスをスピーディに実装していくことを目指している」と、ReGACY Innovation Group Directorの中村京介氏が、「Be Smart Tokyo」の事業概要について説明。「当社は、東京都から採択された『スマートサービス実装促進事業者』として、東京都やサービスの実装先であるエリアマネジメント団体およびその関係企業・団体であるスマートシティ基盤提供者と連携し、スマートサービスの実装を推進している。主に『女性活躍支援』『障がい者支援』『教育格差の是正』の3分野において、スタートアップによるスマートサービスの社会実装プロジェクトを運営しており、2025年度には、新たにスタートアップ3社を加え、計8社の採択事業者の取り組みを支援している」と、プロジェクトにおける同社の役割を紹介した。

続いて、「Be Smart Tokyo」の採択事業者であるAshirase、クロスメディスン、CLACKが、それぞれのプロジェクト概要とこれまでの活動状況について中間報告を行った。Ashiraseは、視覚障がい者向け機器「あしらせ」の開発・提供を行っている。「あしらせ」は、靴に装着するコンパクトな機器で、地図アプリと連動し、足元への振動によってユーザーを目的地へと誘導する。聴覚を邪魔しないことで単独歩行の不安を軽減し、歩く安心感と楽しさを提供する。Be Smart Tokyoの活動では、「あしらせ」と視覚障害者向けナビゲーションアプリ「ナビレンス」を連携し、新宿西口ハルクに実装。屋外利用が主となっている「あしらせ」のサービスを屋内施設に応用し、視覚障がい者の屋外から商業施設への移動をシームレスに支援するとともに、施設内での移動や購買活動を支援している。これまでの活動成果として、ナビレンスコードを通じて屋内情報が取得され、来訪者の買い物につながっていることを確認した。来期は、アクセシビリティ向上と回遊性向上の両立を目指し、屋内移動を自律的にできる「施設内ナビゲーション」の実装を進めていく。

クロスメディスンは、泣き声理解促進アプリ「あわベビ」を開発している。「あわベビ」は、泣き声判別アプリとしては最高レベルの11種類まで泣き声の分類が可能で、赤ちゃんの感情や体調を泡で表現し、ユーザーに伝える。泣き声ストレスを解消することで、産後うつの原因解消につなげていく。Be Smart Tokyoの活動では、企業内の福利厚生として、連携企業の子育て中の都内従業員に、乳幼児泣き声解析アプリを提供。これまでに、福利厚生として3件の導入実績があるという。一方で、自治体や保育園での導入はゼロであり、「あわベビ」の価値のさらなる理解促進を課題として挙げた。中期的には、AI解析技術を様々な子育て支援サービスと連携させ、都民の子育てしやすい環境の整備を行っていく。

CLACKは、機会格差の結果生まれた意欲と主体性の低い中高生に対し、様々パートナーと連携をしながら、スキル支援やキャリア支援、居場所の運営など伴走支援を行っている。Be Smart Tokyoの活動では、都内にデジタル教育を提供する拠点を設置し、自治体等と連携して貧困等の困難を抱える学生を支援している。また、社会貢献型ITソーシングサービス「クエスト」を展開。同サービスでは、連携先企業から、実際にWeb製作業務などを受注し、学生に対価を与えることで、学生の自立促進を図っている。企業が「クエスト」に案件を発注することで、子どもたちに「学ぶ機会」「働く機会」「報酬を得る機会」の3つの機会を創出することができ、企業の社会貢献につながるという。中間報告では、共同土木(Web制作)、東京都千代田区(Web制作)、イノベーシスト(SNS運用)、READYFOR(チラシ制作)などの利用事例を紹介した。

2025年度の新規採択事業者として、セラピア、KAERU、iibaの3社がプロジェクトの概要を説明した。セラピアは、ノーコードツールを活用したシステム開発受託およびノーコード技術のスキルコーチングを提供している。すべての企業や人がデジタルツールを使いこなし、DXを自らの手で実行できる社会の実現に向けた支援を行っている。Be Smart Tokyoの活動では、障がい者手帳アプリ「ミライロ ID」を運営するミライロと連携し、今年8月~10月に受講者を募集。応募のあった約20名の障がい者にノーコード技術のスキルコーチングを実施した。今後の課題としては、スキル習得後の就職先となる連携企業(案件)の確保を挙げ、受講生が就職した企業・施設とセラピアが案件を相互委託することで、案件を持つ市場(自治体・企業)と、人材の受け皿となる連携先をつないでいく考えを示した。

KAERUは、金銭管理の支援が必要な人およびその支援者向けキャッシュレスサービス「KAERU」を開発・提供している。Be Smart Tokyoの活動では、東京都の障がい者・単身高齢者を対象に、「KAERU」を用いたDX化を促進し、支援者と被支援者の利便性向上および金銭管理業務削減を目指している。中間報告として、東京都手をつなぐ育成会の障がい者施設への導入実績を紹介。「KAERU」の導入によって、1回の支援あたり85%の業務削減効果を実現したという。今後は、社会福祉協議会や成年後見人支援への普及促進を図ると共に、地域包括・医療ソーシャルワーカー(MSW)・ケアマネジャーと連携したつなぎ支援に取り組んでいく。

iibaは、子育て世帯向けマップアプリ「iiba(イイバ)」を運営している。同アプリでは、全国のファミリーからの投稿を通じて、子育てに優しい施設・店舗を簡単に探すことができる。また、550名以上のインフルエンサーが参画しており、SNSでも強い影響力を持っている。Be Smart Tokyoの活動では、東京都における各自治体の子育てマップをデジタル化し、加盟店舗を増やすことで地域情報の拡充を図る。自治体連携後は、事業者へのピンの設置/SaaSも提供する。さらに、バウチャー利用を推進し、地域経済の活性化および子育て世帯の利用率向上を検証していく。マップの先にある現地での子育て消費を促進し、新たな経済圏を創出することで、子育てしたい・応援したい社会の実現を目指す。

次に、採択事業者のGATARIと三菱地所が取り組む注目プロジェクト「視覚障がい者を含む、誰もがアートを体験できる音声ガイドコンテンツ」についてトークセッションを実施した。GATARIでは、デジタルとリアルを融合させるMR(ミックスドリアリティ)プラットフォーム「Auris」の開発・提供・運営を手がけている。「Auris」は、cmオーダーでの空間認識トラッキング技術と自然な音声フィードバックによって、視覚障がい者に安全で快適な移動と、施設や空間におけるエンターテインメント体験を提供することができる。

Be Smart Tokyoのプロジェクトについて、GATARI 代表取締役CEOの竹下俊一氏は、「三菱地所と連携し、丸の内ストリートギャラリーで、視覚障がい者を含む誰もがアートを体験できる音声ガイドコンテンツ『耳とからだで聴く彫刻たち』を展開している。同コンテンツでは、丸の内ストリートギャラリーに常設展示されている屋外彫刻を舞台に、『Auris』のMR技術を活用して音声ガイドと空間音響で作品の魅力を伝える新しい鑑賞体験を提供する。視覚情報に依存しないため、視覚障がい者を含む誰もが安全にアートを楽しむことができる」と、耳で作品に触れる新たなアート鑑賞体験を創出したと説明する。「今年7月のサービス開始から約2ヵ月間で、体験者数は146名、延べ体験回数は1200回を超えた。また、1人あたりの体験数が8.3回と多いことから、高い回遊性とエンゲージメントが示された。視覚障がい当事者を含むさまざまな来場者に対して、インクルーシブな体験を提供できたと考えている」と、音声ガイドコンテンツの体験状況を報告した。

三菱地所 エリアマネジメント事業部の丸岡彩氏は、「GATARIとは、2022年に三菱一号館美術館の展覧会でコラボレーションした実績があることから、今回のBe Smart Tokyoでも連携プロジェクトに取り組むこととなった。音声ガイドコンテンツの展開にあたっては、これまでに公共空間を活用した『Auris』の事例がないと聞き、丸の内ストリートギャラリーが最適だと思った。また、同ギャラリーは3年に1度、作品を入れ替えているが、音声ガイドコンテンツを通じて、視覚障がい者を含めてもっと幅広い人々に親しんでもらえる空間にしていきたいと考えた」と、音声ガイドコンテンツを丸の内ストリートギャラリーで展開する背景について教えてくれた。
GATARIの竹下氏は、「丸の内ストリートギャラリーでのサービス提供後、公共空間での聴き取りやすさや没入感向上のため、音声の周波数やリバーブ(残響)の調整を行った。また、MRサービスに慣れていない人でも使いやすいよう操作性にも配慮した。特に、視覚障がい者に対しては、鑑賞中に車道に出てしまわないように対策することの重要性を学ぶことができた。今後も、三菱地所と協力しながら、公共空間の中で、視覚障がい者や一般の人がそれぞれプライベートな体験を楽しめるコンテンツを提供していく。さらに、現実のさまざまな情報と連携し、時間によって変化するコンテンツも実現していきたい」と、三菱地所とのさらなるコラボ展開に意欲を見せていた。

最後に、採択事業者のCuelとメリービズによる「女性のキャリア構築」の取り組みについてトークセッションを実施した。Cuelは、女性専用のオンライン経理・財務スクール「CuelCollege」を運営すると共に、経済的困窮を抱える女性や望む働き方ができていない女性の就労支援を行っている。同社 代表取締役の鈴木ひとみ氏は、「『CuelCollege』では、これまでに累計480名以上の経理人材を育成してきた実績がある。Be Smart Tokyoのプロジェクトでは、東京都の人材紹介会社や経理業務専門のBPOベンダーと連携し、スクールの卒業生を就労にシームレスにつなぐ仕組みの構築を進めている。今後は、経理業務未経験者の採用促進に向けて、スクールでの“学習履歴”を評価してもらえるよう企業に呼びかけていく。将来的には、女性だけでなく、男性向けにも『CuelCollege』を展開し、幅広く経理人材を育成していきたい」と、プロジェクトの今後の展望を語った。

メリービズは、企業を支えるバックオフィスにおける業務課題の解決および、日本全国のプロフェッショナル人材の活躍支援を進める事業を推進。BPaaSオンラインアウトソーシング事業として「バーチャル経理アシスタント」、DXコンサル事業として「経理DX」を展開している。同社 社長室室長の石川淳一氏は、「Cuelと連携した取り組みでは、『CuelCollege』のプログラムに参画し、経理業務専門のBPOベンダーとして、卒業者の就労支援や経理業務のアウトソーシングを行っている。この取り組みを通じて、未経験者が経理業務にチャレンジするハードルを下げると共に、卒業者にはライフスタイルに応じた多様な働き方を提供していく。また今後は、卒業者と企業のマッチングを地域内で完結できる仕組みの構築を目指し、未経験者の育成や案件管理、就労への動線づくりに取り組んでいきたい」との考えを述べた。
ReGACY Innovation Group=https://regacy-innovation.com/
東京都スマートサービス実装促進プロジェクト(Be Smart Tokyo)=https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp/
- #Ashirase
- #Be Smart Tokyo
- #CLACK
- #Cuel
- #GATARI
- #iiba
- #KAERU
- #ReGACY Innovation Group
- #イベント
- #クロスメディスン
- #スマート東京
- #セラピア
- #メリービス
- #三菱地所
- #採択事業者
- #東京都
- #東京都スマートサービス実装促進プロジェクト