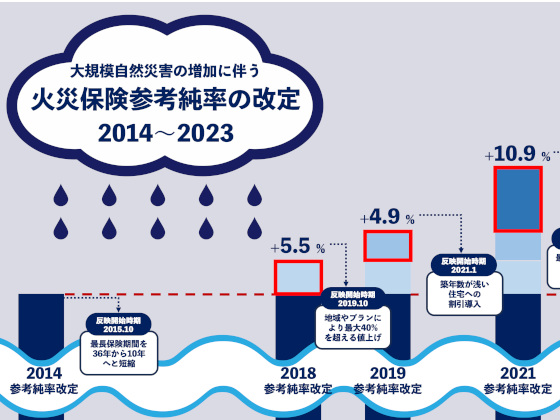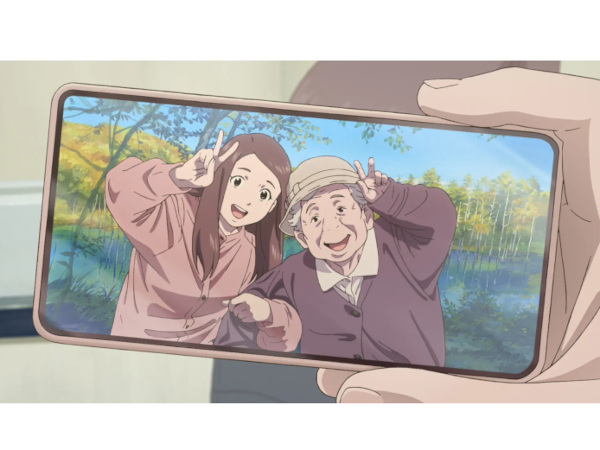- Study&Work2025/10/29 17:31
中谷財団、「なぜRikejoが増えないのか」をテーマに科学教育セミナーを開催、理系分野を目指す女子中高生の支援が重要に

BME(Bio Medical Engineering)分野の発展を通じて、日本のイノベーションを促進させるため、表彰事業および新しい研究や技術開発を支援する助成事業など幅広い活動を行っている中谷財団は、「なぜRikejoが増えないのか」をテーマとした科学教育セミナーを10月21日に開催した。男女雇用機会均等法が施行されて40年がたった今、日本においての理系女子の割合はまだ少なく、特に研究者に至っては、OECD加盟33ヵ国中で最下位となっている。そこで今回のセミナーでは、それぞれの立場で「Rikejo」を増やすことに積極的に取り組んでいる先生を招いたパネルディスカッションを行った。
パネルディスカッションでは、千葉大学次世代 in Vivo研究探索センター 特任教授の塩見春彦先生がコーディネーターを務め、関西学院大学副学長・情報化推進機構 機構長の巳波弘佳先生、大阪公立大学大学院 理学系研究科物理科学専攻 教授の細越裕子先生、東京大学生産技術研究所 次世代育成オフィス 准教授の川越至桜先生がパネリストとして参加し、教育の立場からの「Rikejo」を増やす取り組みやジェンダーレスの社会と「未来像」などについて意見を交わした。

まず、理系分野に進む女性の現状について、コーディネーターの塩見先生が解説。「私が約10年前に作った資料では、理系女子が増えない背景として、『家事・育児・介護は女性の仕事』『研究や研究室の運営は男性向き』という潜在意識や、『理系だと就職/結婚できない』という先入観、専業主婦を前提とした制度や仕組みなどを挙げている。ここから約10年が経った現在、日本の女性研究者の割合は増加傾向にあり、2024年には18.5%となった。しかし、OECD加盟国33ヵ国の中ではいまだ最下位となっている。また、ジェンダーギャップ指数を見ても、日本は2006年から2025年までほとんど変化がなく、男女平等が進んでいないのが実状。理系女子に対する先入観や無意識の壁は、今も根強く残っている」と指摘する。

こうした現状の中、「Rikejo」を増やすために実施している活動について、大阪公立大学大学院の細越先生は、「私は女子STEAM人材育成研究所の所長を務めており、文部科学省の『女子中高生の理系進路選択支援事業』にも関わっている。女子STEAM人材育成研究所では、女子中高生に対して、理系分野の幅広さ、奥深さ、楽しさを伝え、多様な進路選択を支援すること、ひいてはSTEAM(科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・芸術(Arts)・数学(Mathematics)分野の理系女性の育成とダイバーシティ推進を目指している。具体的な取り組みとしては、関西圏の国公立大学の連携事業として『女子中学生のための関西科学塾』を展開し、理系分野に関する興味・関心を喚起するとともに、多様なロールモデルを提示している」と、女子中高生が理系分野に進む後押しをしているという。
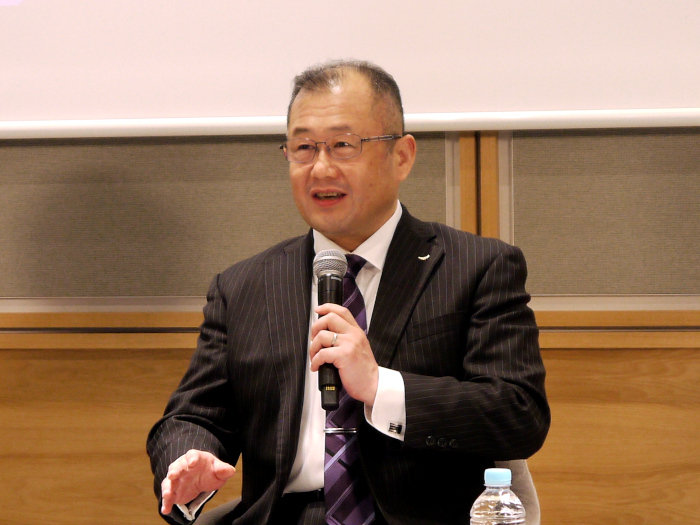
関西学院大学の巳波先生は、「当大学では、AI活用人材育成プログラムを推進しており、私はそのプロジェクト統括を務めている。現在、同プログラムを受講している学生の男女比は1:1となっており、学内における男女の偏りはなくなりつつある。これは、理系を目指したい女子学生に対して、余計なバイアスを取り除くことで、積極的に理系分野に進んでいけることを示している。一方で、理系分野に興味がありながら、実際に理系学部に進学する女子中高生の割合は、かなり低いのが実状。この背景には、中学・高校時代の進路指導の問題と、周囲の同調圧力が大きく影響していると考えている」と、最先端のAI活用人材を育成する視点から「Rikejo」の課題を語る。

東京大学の川越先生は、「当大学の生産技術研究所では、2011年に『次世代育成オフィス』を設立し、様々な機関や企業と連携して次世代のイノベーションを創り出す人材を育成する教育活動を創出する『教科・科目横断 STEAM型教育プログラム』を展開している。その中で、未来の科学者のための駒場リサーチキャンパスの公開や高校の授業内での学術指導、女子中高生の理系進路選択支援などに取り組んでいる。特に、グローバル科学技術人材の育成プログラム『UTokyoGSC-Next』では、小学生・中学生向けにSTEAM型教育を実践しており、受講生の半数が女子生徒になっている」と、男女の隔たりなく次世代の理系人材育成に力を注いでいると強調した。

では、今後「Rikejo」が活躍できる、開かれたジェンダーレス社会にするためには、何がポイントになるのだろうか。巳波先生は、「様々なポイントがあると思うが、社会基盤の観点から、もっと柔軟な働き方ができるようにする必要があると感じている。コロナ禍を経て、一時はテレワークが普及したが、現在はオフィス出社に戻りつつある。特に家庭を持つ女性にとっては、育児などを考えると、自宅でテレワークができると負担が軽減され、とても働きやすい。テレワークに限らず、理系分野でも、自分に適した働き方ができる環境を整えることが『Rikejo』の活躍にもつながる」との考えを述べた。
細越先生は、「今まで男女差といわれてきたことの多くは、実は性差ではなく個人差であったと思う。これからは、性別に関係なく、男性も女性も自分の好きなことを自由に選べる社会にしていくことが大切だと考えている。今は女性支援という言葉が注目されているが、女性が働きやすい社会は、間違いなく男性も働きやすくなる。それだけに、女性支援の活動に男性も積極的に参加してほしい。理系分野も含めて、社会全体が男性・女性の区別なく自由に働けるように努力していきたい」と話していた。
川越先生は、「私も男女問わず、誰もが自由に理系分野で働ける社会構造や環境を整えていくことが重要だと思っている。私は学生時代、物理学科で実験をした時に、ペアになった男性から『なぜ女子が物学をやっているのか』といわれ、実験装置に触らせてもらえなかった経験がある。まずは、こうした偏見をなくしていく必要がある。理系分野に進む女性は、今も少数派だが、その中で社会全体が理系女子のことを認め、活躍できる環境を作っていくことが、ジェンダーレス社会の実現にもつながっていくのではないか」と、「Rikejo」の存在が社会に広く認知されることを願っていた。