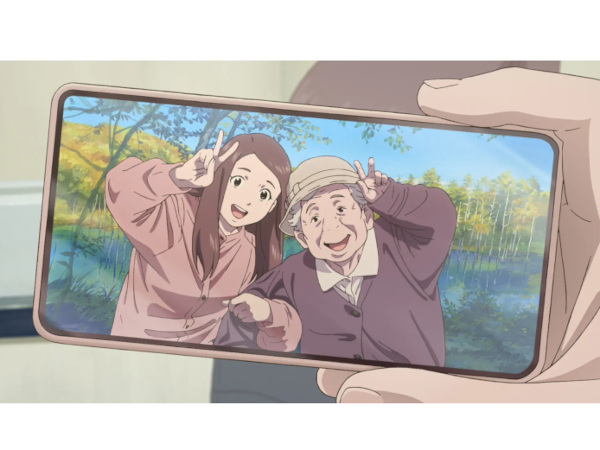- Hobby&Culture2025/09/05 18:15
明治安田総合研究所、調査レポート「キダルトが存在感を放つ玩具市場」、玩具市場は少子化のなかでも成長を続けている

明治安田総合研究所は、調査レポート「キダルトが存在感を放つ玩具市場」を発表した。
玩具市場は少子化のなかでも成長を続けている。玩具を楽しむ大人“キダルト”層の購買が勢いづいていることが背景にある。特に単身世帯では、年齢にかかわらず玩具への支出が顕著に拡大している。
多様な娯楽のなかで玩具消費が伸びた理由はいくつか考えられるが、特に(1)SNS上の「見せる」消費の拡大、(2)相対的なコスパの良さ、(3)コロナ禍を経たコミュニティの変化が上手く重なったことも大きい。
キダルト消費は玩具を通じた「共感」や「つながり」を重視する価値観を反映しており、企業には質の高いコミュニティマネジメントなど、消費者のロイヤルティを高め、維持する姿勢がいっそう求められる。
少子化が進むなか、意外にも日本の玩具市場は成長を遂げている。日本玩具協会によれば、2024年度の国内玩具市場の規模は1兆992億円と過去最高を更新し、10年前から約1.4倍に拡大した。この間、15歳未満人口は約14%減少しており、市場の拡大は少子化の進行と対照的である。
この成長を支えているのは、玩具を楽しむ大人“キダルト”と呼ばれる層である。キダルトはKid(子ども)とAdult(大人)を組み合わせた造語であり、“子どもの心を持つ大人”を意味する。従来の「玩具=子どものためのもの」というイメージは変化しつつあり、近年は大人の趣味や自己表現の手段として広がってきた。
メーカー各社は、大人が自分のために買いたくなる商品を積極的に展開している。日本玩具協会の調査によると、2024年度に前年度から売上が伸長した商品カテゴリーの上位は、(1)ハイテク系トレンドトイ、(2)キャラクター玩具、(3)ぬいぐるみとなっている。ハイテク系トレンドトイでは、1990年代に一世を風靡した「たまごっち」の復刻版「Original Tamagotchi」が再びブームを巻き起こしたほか、キャラクター玩具では、子どもから大人までを対象に世界大会も開催されている現代版ベーゴマ「BEYBLADE X」が人気を集めた。ぬいぐるみでは、英国発ブランドの「Jellycat」など、柔らかな質感とデザインの愛らしさが大人からも高い支持を得ている。

総務省の「家計調査」を見ると、玩具への支出額は全体として増加しているが、特に子どものいない単身世帯の伸びが顕著である。2024年の年間平均支出額は1万4498円と2014年比では約3.5倍となり、子どものいる世帯が含まれている二人以上世帯(1万2367円)を上回った。

スポーツ用品やペット用品、文房具などが含まれる教養娯楽用品に占める玩具の割合は、2014年の9.8%から2024年に19.9%へ高まっている。教養娯楽サービスなどを含めた教養娯楽全体でも同様の傾向である。世帯の消費支出は所得の増加に伴って伸びていくと考えられるが、2014年と2024年を比較すると、単身世帯の可処分所得の伸びは+12.7%と、二人以上世帯(同+23.4%)を下回っている。いかに単身世帯で玩具への消費意欲が高まっているかが分かる。

また、単身世帯について年齢階級別に見ると、2024年における35~59歳以下の支出額は1万3107円と、34歳以下(2万845円)を下回っているものの、2014年からの伸び率は34歳以下より高く、若い世代に限らず玩具を楽しむ人が増えている様子が確認できる。家計調査で確認できる支出額はまだそれほど大きくないが、今年3月には玩具量販店大手のトイザらスがキダルト向け商品のみを集めた専門店を出店するなど、企業側の動きは一段と活発化している。キダルト消費はさらなる拡大が期待される。近ごろは物価高で節約志向が高まるなか、生活必需品などの必要な支出を抑えつつ、好きなことにお金をかける“メリハリ消費”が広がっている。もっとも、多様な趣味や娯楽があふれる現代において、なぜ「おもちゃ」が選ばれているのか。理由はいくつか考えられるが、特に(1)SNS上の「見せる」消費の広がり、(2)相対的なコスパの良さ、(3)コロナ禍を経たコミュニティの変化が上手く重なったことが大きい。

近年は、モノを購入すること自体に加え、それをどう楽しみ、どう「見せるか」に価値を置く消費スタイルが広がりをみせている。SNSでの共有がその中心にあり、他者からの共感や承認を得ることが購買動機となるケースも少なくない。キダルト層においては、ぬいぐるみと一緒に外出して写真を撮影し、SNSに投稿する「ぬい活(ぬいぐるみ活動)」などが新たな遊び方となっている。玩具の商品群においては、カプセルトイやトレーディングカードなど低価格帯で手に取りやすいものも多く、趣味や娯楽費が全体として高騰するなかで、手軽に楽しめるコスパの良い選択肢となっている。また、豊富な商品展開は消費者の自己表現の幅を広げ、SNS 上の「見せる消費」との相性も良い。SNSは、企業が商品の魅力を訴求する重要なチャネルであると同時に、ユーザー同士の交流の場として機能しており、購買促進だけでなく、コミュニティ形成にも一役買っている。コロナ禍を経てこれまでの人付き合いが整理されるなか、SNS を通じて友人を見つける人は少なくない。マーケティングリサーチ・市場調査を行なうアスマークによると、コロナ禍を経て交友関係が減少したとの回答が約3割となった一方、SNS上で共通の趣味や価値観を持つ友人に出会えたと回答した人は20代で約6割、20~50代でも4割に上っている。SNSサイトのInstagramでハッシュタグ使用数を見ると、「ぬい活」や「リカ活」など、キダルト層に人気の玩具に関連するハッシュタグが多く確認できる。

SNSでのつながりなどもきっかけに、オフラインイベントも盛んに開催されている。現在の玩具市場において最大の市場規模を誇るのはカードゲーム・トレーディングカードだが、面白法人カヤックによれば、同社のイベント運営支援プラットフォームTonamelを活用したトレーディングカードゲームの大会開催数は昨年に3万6311件に上ったとのことである。今年は8月26日時点で3万6477件と、すでに前年を上回っている。仮にこのペースが維持されれば年間開催数は5万件を超える見通しであるが、同社によると足元で開催ペースが上がっているとのことである。年齢に関係なく価値観でつながるコミュニティがオン・オフラインともに拡大している。

キダルト消費の広がりは、従来の玩具の「所有」に加え、「共感」や「承認」、「つながり」を重視する価値観の高まりを反映している。SNS上の見せる消費や、オン・オフラインを問わない交流が活発になる背景には、消費者が商品そのものだけではなく、その先にある体験や他者との関係性に従来以上に価値を見出していることを示している。
多くの企業にとって、事業の安定性や収益の持続可能性を高めるうえで、消費者のロイヤルティを高め、維持することは重要課題となっている。ロイヤルティの高い消費者は、企業や商品ブランドに対して信頼と愛着を持ち、継続的な購買を通じて収益を支えるとともに、時に他の消費者への“伝道者”としての役割も果たす。
そのなかで改めて注目されるのが、コミュニティマネジメントの重要性である。ファン同士が活発に交流することのできるコミュニティは、企業や商品ブランドに対する愛着やエンゲージメントを高める。例えば、ブロック玩具を提供するLEGOは、特に熱心なファンを公式アンバサダーに認定し、企業とファンコミュニティの橋渡し役として活動してもらうことで、ファン全体とのつながりを強化している。一方で、コミュニティの健全性を
保つ取り組みも欠かせない。熱量の高まりが排他的な言動につながる場合もあり、企業側がルールづくりや対話の場を整え、心理的安全性が確保された良質なコミュニティを育てていくことも重要である。
明治安田総合研究所=https://www.myri.co.jp