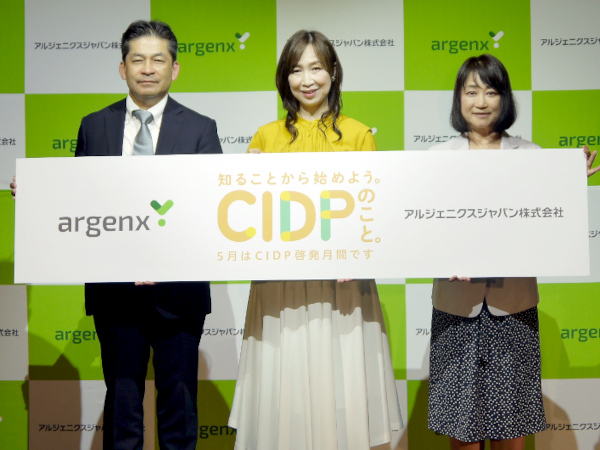- Health&Medical2025/05/15 21:17
アルジェニクスジャパン、森口博子さんが「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(CIDP)」について学ぶメディアセミナーを開催

アルジェニクスジャパンは、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(以下、CIDP)啓発月間プロジェクトの一環として、メディアセミナー「ゲストの森口博子さんと『知ることからはじめよう。CIDPのこと。』」を5月8日に開催した。今回のセミナーでは、ゲストとして歌手の森口博子さんを招き、埼玉医科大学総合医療センター 脳神経内科 教授、日本末梢神経学会 理事長の海田賢一先生、およびCIDP患者である全国CIDPサポートグループ 理事長の鵜飼真実氏による講演を通じて、CIDPがどのような疾患なのかを学んでもらった。そして、セミナーの最後には、森口さんがCIDPに関する理解度クイズに挑戦した。

「CIDPは、自己免疫が関係している脱髄性の末梢神経障害で、主な症状として四肢筋力低下と感覚障害が現れる。8週間以上の経過で進行あるいは再発・寛解を繰り返す慢性疾患となる。脱髄とは、末梢神経の軸索を覆う髄鞘(ミエリン)が攻撃され、炎症を生じて脱落することで、神経細胞から筋肉への情報がスムーズに伝わらなくなる」と、CIDPの病態について埼玉医科大学総合医療センターの海田先生が解説。「2021年の国内におけるCIDP推定患者数は約4180人で、有病率は10万人あたり3.3人、発症率は10万人あたり0.36人。平均発症年齢は52歳、男女比は1.5:1と男性に多い疾病となっている。世界各国の状況を見ても有病率は10万人当たり1~7人程度である」と、世界的にも希少な自己免疫疾患であると強調した。
「CIDPでは、手足の近位・遠位の筋力低下、しびれや感覚低下などの感覚障害、腱反射の低下・消失の他に、疲労や灼熱感、痛み、手の震え、複視などの症状がみられる。これらの症状には個人差があり、障害される神経の部位や障害のされ方によって、典型的CIDPとCIDPバリアント(異型)に病型が分類される。そして、病型間で神経生検の病理が異なるため、診断が非常に難しい疾病でもある」とのこと。「日本神経学会による『CIDP/MMN診療ガイドライン2024』では、CIDPの治療目標を『身体機能の長期的改善を目指す』としている。また、治療方針として、身体機能障害をできるだけ速やかに改善し、改善した状態を長期間維持する。合併症の適切な管理によってQOLの改善に努める。薬剤の適正使用によって有害事象の発現を予防あるいは低減し、生じた場合は適切に対応する。治療法の選択には患者と情報を共有し、協働的意思決定を行うことを挙げている」と、CIDPの治療目標と治療方針について説明した。
「CIDPの治療法としては、活動期における寛解導入療法と安定期における維持療法があり、副腎皮質ステロイドや経静脈的免疫グロブリン療法などが行われる。また、CIDPの病態生理はまだ解明されていないが、近年の研究でIgG自己抗体による末梢神経の損傷が関与していることがわかってきている。そこで、IgG自己抗体を主病態と仮設した新たな治療法の開発が進められている」と、CIDP治療の最前線についても教えてくれた。

続いて、CIDP患者である全国CIDPサポートグループ 理事長の鵜飼氏が、同グループが実施したCIDPの患者実態調査について説明した。「全国CIDPサポートグループは、2006年に13名の患者と家族が全国から集い発足した、CIDPとその類縁疾患の患者会となる。同グループの会員203名を対象に実施した患者実態調査によると、CIDPの確定診断を受けている人は81%を占め、そのうち典型的CIDPが41%、CIDPバリアントが17%だった。病態の経過タイプについては、慢性進行タイプが43%、再発寛解タイプが32%となっている」と、患者の病型について紹介。「確定診断までに受診した病院数は1ヵ所が28.9%、3ヵ所が25.3%、2ヵ所が24.7%。確定診断までに要した期間は3ヵ月以上6ヵ月未満が23.7%、3ヵ月未満が18.7%、6ヵ月以上1年未満が17.7%だった。2017年度に実施した実態調査では、確定診断までに6年以上かかっている人が18%もいたが、今回は8%に減少していた」と、CIDPの診断精度が高まってきていることがわかった。
「通院する際の介助の必要性について聞くと、『1人で通院できる』が70%、『一部付き添い、介助が必要』が23%、『全て付き添い、介助が必要』が7%だった。一方で、通院する上で課題・不安に感じることは、移動関連が73%を占めた」と、自分1人で通院できなくなった場合や、付き添いの人の仕事や交通費などを心配する声が挙がっていたという。「現在通院・入院している医療機関での診察や治療についての満足度は、87.6%が『満足している』と回答し、2017年度調査の79%から大きく上昇した。治療方法のバリエーションが増えたことで症状がコントロールできるようになってきたことが満足度の向上につながったと推測している」と、治療法の進化にともない満足度も高まっていると分析していた。

ここで、ゲストの森口博子さんを迎え、埼玉医科大学総合医療センターの海田先生、全国CIDPサポートグループの鵜飼氏とのトークセッションを行った。海田先生と鵜飼氏の講演を聞いた森口さんは、「セミナーが始まる前は、CIDPがどんな病気なのか、ほとんど知らなかったが、講演を聞いて想像以上に大変な病気であることがわかった。病気を抱えながら、確定診断されるまでに何ヵ所も病院を受診したり、何年もかかった人がいると聞いて、胸が締め付けられた。CIDPという病気について、もっと多くの人に知ってほしいと思っている」と、CIDPへの理解が深まったと話していた。

トークセッションでは、鵜飼氏がCIDP患者として、症状が現れた時の状況や確定診断に至るまでの経緯、病気との付き合い方など、自身の体験談を語ってくれた。また、海田先生は、専門家の立場から、CIDPの確定診断までに時間がかかる理由やCIDP患者と医師とのコミュニケーションの重要性などについて教えてくれた。トークセッション中、森口さんは、CIDPに関する率直な疑問を二人に投げかけ、病気や患者の抱える課題について積極的に学んでいた。

そして、セミナーの最後に、森口さんにはCIDPに関する理解度クイズに挑戦してもらった。クイズは、「CIDPの一般的な症状として正しいのは?」、「日本にいるCIDP患者の数に一番近いのは?」、「CIDPの治療には何科を受診するのが正解?」の3問。森口さんは、悩みながらも見事全問正解を達成し、「今回のセミナーを通じて、自分が病気だとわかったときに、その病気と向き合っていく強い気持ちが大切だと感じた。CIDPについては、まだ知らない人が多いと思うので、私自身SNSなどを通じて、この病気のことを多くの人に伝えていきたい」と、CIDPの啓発活動に取り組んでいくことを誓っていた。
アルジェニクスジャパン=https://www.argenx.jp/
全国CIDPサポートグループ=https://cidpsgj.org/
- #CIDP
- #アルジェニクスジャパン
- #セミナー
- #全国CIDPサポートグループ
- #埼玉医科大学総合医療センター
- #感覚障害
- #慢性炎症性脱髄性多発根神経炎
- #慢性疾患
- #日本末梢神経学会
- #森口博子さん
- #治療法
- #筋力低下
- #自己免疫