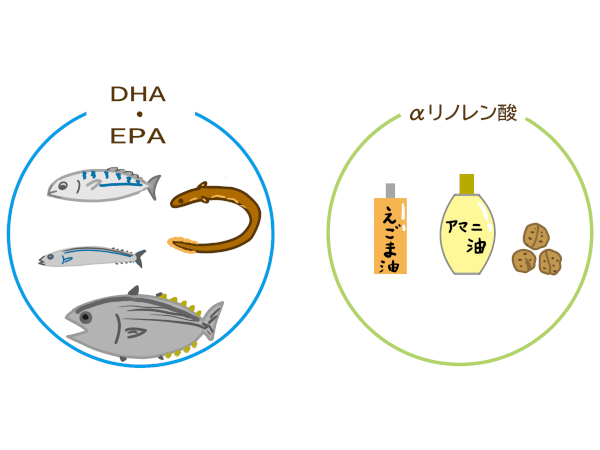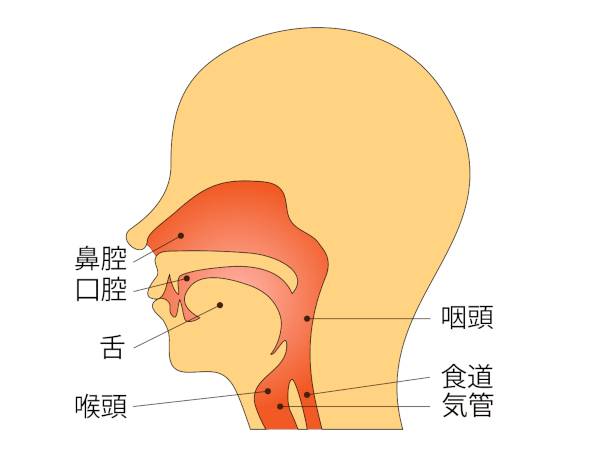- 健康管理!教えて!!2025/09/12 23:02
ストレスが子どもの脳に与える影響とは? 大人だけでなく子どもにも「うつ病」のリスクが

子どもは、主に家庭環境(虐待、近親者の死、両親の不和や離婚、兄弟との比較など)や学校生活(体罰、いじめ、友人関係、担任教師との相性、学業不振など)において、ストレスを生じやすくなります。特に、子どもの心や体が一番守られるべき場である家庭において、守らなければいけない人である「近親者」からの虐待や言葉の暴力といった強いストレスは、脳に大きな影響をおよぼすとされています。
子どもに対する強いストレスは、脳の一部の発達を一時的に止め、脳自体の機能や神経構造に永続的なダメージを与えることが示唆されています。また、ストレスによる心の病気で治療を受けている大人は、心の病気のない健康な大人と比べて、子ども時代に強いストレスを経験している傾向があるといわれています。
ストレスによる行動や行為としては、指しゃぶり、チック、爪を噛む、抜毛、歯ぎしり、舌打ち、家庭内での反抗や暴力などがあります。また、落ち着きがなく動き回る、物事に対して集中して取り組めない、忘れ物が多い、多動や衝動的な行動が多いなどには、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の可能性があります。ADHDは、軽度の発達障害の1つであり、問題行動が繰り返されるもとには、脳の機能不全があると考えられています。
強い社会的ストレスを受けることで発症するうつ病は、大人がかかる病気であり、従来は成長過程の子どもには発症しないと考えられてきました。しかし、最近になって子どももうつ病になることが知られてきています。特に、男子は中学1年生から、女子は小学6年生から、「うつ傾向」と診断される子どもが増えてくるそうです。子どもは、精神症状よりも身体症状を訴えるため、周囲の大人は子どものうつ病の兆候(睡眠障害、食欲不振、問題行動など)を見逃さないよう早期発見に努めることが大切です。(監修:健康管理士一般指導員)