- Drink&Food2025/05/02 20:55
キリン、早稲田大学学生向けに適正飲酒セミナーを開催、若年層の飲酒に関わる事故の発生状況について触れ自分事化を促す

キリンホールディングスは、酒類を扱う企業の社会的責任を果たすべく、消費者のお酒との正しい付き合い方についての理解浸透に取り組んでいる。特に4~5月は人の集まる場が増加したり長期休暇で遠出したりすることが多く、飲酒に関わる事故が増加するリスクがあり、さらなる啓発が必要と考えられる。そこで、5月の長期休暇を前に、学生に対する適正飲酒啓発の必要性について4月25日、早稲田大学と適正飲酒セミナーを共同開催した。同セミナーでは、若年層の飲酒に関わる事故の発生状況についても触れ、大学生たちに自分事化を促した。また、5月の長期休暇に増加傾向の飲酒運転についても取り上げ、時期的に高まるリスクに対しても注意喚起を行った。
まず、早稲田大学 学生部 学生生活課 担当者と早稲田大学学生健康増進互助会 担当学生が今回、適正飲酒セミナーを開催するに至った経緯を紹介。その後、キリンアンドコミュニケーションズ 人材開発室 菊池祥子氏を講師に招き、大学生たち(20歳未満の学生を含む)に「お酒と自分と仲間を知ろう!」編と題した適正飲酒セミナーを行った。
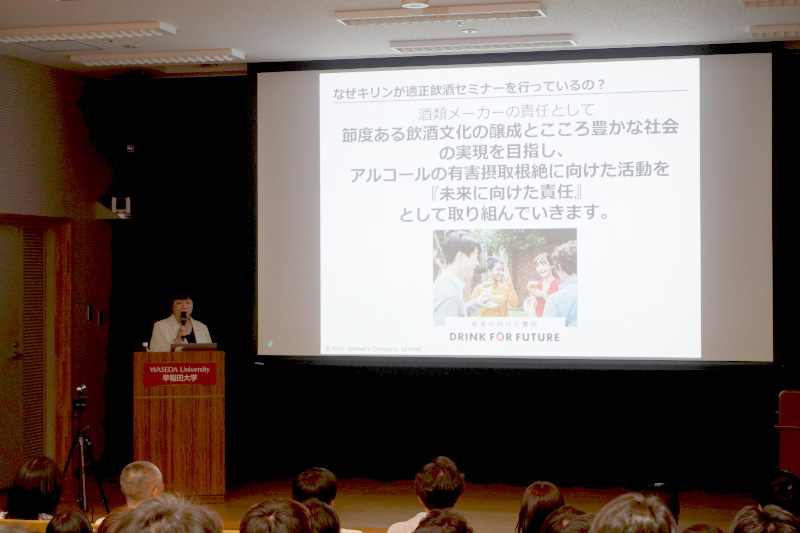
それでは、お酒に酔うとはどういうことなのだろうか。「お酒とは、日本の酒税法では、アルコールが1%以上含まれた飲み物のことを酒類と定義している。お酒に含まれるアルコールとは、酵母によって糖を発酵することで生まれるエチルアルコールを指す」と、お酒の基本について解説。「飲んだお酒は、肝臓によってアルコールが分解される。アルコールは血液によって脳にも運ばれ、脳の神経細胞に作用し、麻痺させる。これが酔った状態とされる」と、血液中にどのくらいのアルコールが巡っているかによって、酔いの状態が変わってくるのだと説明する。「酔いの程度として、血中アルコール濃度の目安(%)と、アルコール度数5%のビールの目安量でみてみると、360ml1本は爽快期、500ml1~2本でほろ酔い期、500ml~3本で酩酊初期、500ml4~6本で酩酊期、500ml7~10本で泥酔期とされる。爽快期は爽やかな気分で、陽気で皮膚が赤くなるのが特長。判断力が少し鈍る。ほろ酔い期はほろ酔い気分で手の動きが活発。抑制がとれてしまい、体温が上がる。脈も速くなる。酩酊初期は気が大きくなり、大声でがなりたてる。怒りっぽくなり、立てばふらつく。酩酊期は千鳥足になり、何度も同じことをしゃべる。呼吸が速くなり、吐き気や嘔吐が起こる。泥酔期はまともに立てず、意識がはっきりしない。言語もめちゃめちゃ」と、酔いの程度とその特長について語る。「500ml10本以上で昏睡期になるとされる。この状態には絶対にならないようにしなければいけない」と警告。「昏睡期は揺り動かしても起きず、大小便は垂れ流し。呼吸はゆっくりと深く、命に危険が及ぶ可能性もある」と、医療機関に緊急搬送しなければいけない状態であると訴えた。

キリンでは、自分の体質を知って賢く飲むために、アルコール体質チェックを配布。体内で肝臓がアルコールを処理するには時間がかかる。個人差はあるが、ビール500mlを分解するのに要する時間は男性が約4時間、女性では約5時間を目安にしてほしいといわれている。飲酒後に顔が赤くなる人や、睡眠時、空腹時では、さらに時間を要するとのこと。

アルコール体質チェックパッチを腕の内側に貼って、20分経ったら、聖獣麒麟マーク部分をちぎって剥がす。剥がした部分の皮膚の色とインデックスを比較して判定すると、自分は全く飲めない人なのか、アルコールに弱い人なのか、アルコールに強い人なのかが判断できる。アルコール体質チェックで自分の体質を知るだけでなく、もともとお酒に弱い体質の人がいることも知って、周りに配慮することも大切であると促していた。

「身体や精神への影響を知るには、お酒の濃さを表す『アルコール度数』ではなく、お酒に入っている『純アルコール量(g)』で考える必要がある」と、純アルコール量に注目してほしいという。「お酒に含まれる純アルコール量は食品のエネルギー(kcal)のようにその量を数値化できる」と、純アルコール量=飲酒量(ml)×アルコール濃度(%)×比重0.8で、お酒に含まれる純アルコール量をチェックしてほしいと呼びかけた。「厚生労働省では、生活習慣病のリスクを高める飲酒量として、1日あたりの純アルコール摂取量は男性が40g以上、女性が20g以上とされている。個人で異なるものの、1日あたり男性は20g、女性は10g程度でほろ酔い程度になるとされる。当社のお酒の一部の缶には、1本あたりの純アルコール量が記載されているため、どのくらいアルコールを摂取したかを把握できるようになっている」と、純アルコール量でどのくらいお酒を飲んだのかを把握してほしいと呼びかけた。「ちなみに、女性は男性に比べて体内の水分量が少なく、肝臓が小さい傾向にありお酒の影響を受けやすい。女性は男性の半分から2/3程度が良いとされている」と、女性はお酒に弱い体質なのだと話していた。
「20歳未満の飲酒がいけない理由として、(1)脳機能を低下させる。(2)肝臓などの臓器に障害を起こしやすくなる。(3)性ホルモンの分泌に異常が起きる。(4)アルコール依存症になりやすい」とのこと。「20歳未満者が飲酒をした場合、処罰されることはないが、補導の対象となる。補導されると警察署へ連れていかれ、その場で指導を受け、学校や親へ連絡が入る」と、20歳未満の飲酒は絶対にしてはいけないと強く訴えた。「また、日本人は欧米人に比べて44%が遺伝的にお酒に弱い体質とされている。お酒に弱い体質は変わることはない。頭が痛くなったり、気分が悪くなったりする。無理して飲んではいけない」と、日本人はお酒に弱いということを自覚して、無理して飲まないようにしてほしいと訴えた。

次に、アルコール・ハラスメント(アルハラ)について解説。「アルハラは飲酒にまつわる人権侵害。命を奪うこともある危険な行為。イッキ飲み防止連絡協議会では、飲酒の強要、イッキ飲ませ、意図的な酔いつぶし、飲めない人への配慮を欠くこと、酔ったうえでの迷惑行為--をアルハラと定義している」とのこと。「短時間に多量の飲酒をすると、急性アルコール中毒を起こす可能性がある。純アルコール60g以上の一時多量飲酒では、酩酊による怪我をする危険性も高まる」と、一時多量飲酒や飲酒の強要は絶対に避けるべき行為なのだと語気を強める。「急性アルコール中毒の搬送者(計1万1554名:2022年)を年代別にみてみると、20代男性が2769名、20代女性が2783名と他の世代を大幅に上回っている。アルコールに慣れていない分、影響を受けやすく、自分に合った飲み方がわかっていない場合、大量のお酒を短時間で飲み、血中アルコール濃度を急激に高めてしまう」と警告する。「決して、急いで飲まないようにする。お酒は短時間で飲んだり、一気飲みをしたりすると、急性アルコール中毒で死に至ることがある。とても危険な行為」と、急いで飲まない、飲ませないことが大切なのだと強調した。
「急性アルコール中毒には、お酒に強い人も要注意」と警鐘を鳴らす。「ゲームなどで順番でまわりに促されて飲んだり、飲まない人の代わりに飲んだり、まわりの人がもう飲めないので、場の雰囲気を読んで飲むことを引き受けるといった行為はとても危険」と警告していた。「また、飲酒の強要は犯罪で、脅迫して無理やり飲ませた場合は強要罪、最初から酔いつぶすことを目的に飲ませると傷害罪、それらの行為をはやしたてたりすると、傷害現場助勢罪、酔いつぶれた仲間に対し必要な保護をしなかった場合は保護責任者遺棄罪、その結果、死に至った場合は保護責任者遺棄致死罪となる」と、飲酒の強要に関わる罰則について言及した。
「お酒を断るには、法律の力を借りたり、相手のことを心配したりする。また、正確な知識を使ったり、人の力を使う。違う提案も効果的。気持ちを素直にいうことも、ときには大切。きっぱり断ってほしい」と、お酒の断り方について、様々なシチュエーションを想定した断り文句を挙げて、断ることの大切さを説いた。「断りづらいときは、トイレに避難したり、席を外して、戻って来たときは、安全そうな席に座る。よく飲む人、飲ませる人の隣は避ける」ことをすすめていた。

「少量のお酒を飲んだだけでも身体に様々な影響が生じるだけに、飲酒運転は絶対にしてはいけない。自動車やバイクだけでなく、電動キックボードや自転車も乗ってはいけない」と、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力等が低下し、わずかな反応の遅れなどが事故につながるだけに、車やバイクだけでなく、自転車や電動キックボードも同様に飲酒運転となるので注意してほしいと呼びかけた。「ちなみに、自転車は呼気検査の対象。酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる」と、自転車の酒気帯び運転は罰則が強化されていると警鐘を鳴らしていた。
「健康に気遣いながら、個人にあったほどよい飲み方でお酒と楽しくつきあってほしい」と菊池氏。「水やソフトドリンクを間にはさみながら飲んだり、お酒を水や炭酸などで割るのもよい方法。アルコールによる胃への刺激も弱まる」と、ほどよいペースで、心地よい時を過ごせる一杯を楽しんでほしいという。「それぞれが、自分の体質と仲間のことも知ってそれぞれのペースで好きな飲み物を楽しむようにしてほしい」と、飲む人も飲まない人も一緒に楽しめる乾杯が大切だと話す。「お酒の場でも、ソフトドリンクやノンアルコール飲料を選択することもできる」と、キリンでは、様々なソフトドリンクやノンアルコール飲料を展開しているため、色々な飲み物でコミュニケーションを楽しんでほしいと訴えた。
質疑応答では、学生たちから多くの質問が寄せられた。「安いお酒で悪酔いするのか」「少しのアルコール摂取であれば健康になるという人もいるが本当か」「ストローで飲むと酔いやすいのか」など。ちなみに、安いお酒を飲むと酔うと感じる人は、安いお酒が原因ではなく、そのお酒に含まれている成分が身体に合わない可能性があるとのこと。また、アルコールは嗜好品であるため、健康的な身体に導く医薬品ではないという点も強調していた。なお、ストローで飲んでも酔いやすくなることはないとも話していた。
キリンホールディングス=https://www.kirinholdings.com/jp
- #アルコール
- #アルコール・ハラスメント
- #アルコール体質チェック
- #アルコール度数
- #アルハラ
- #キリン
- #キリンアンドコミュニケーションズ
- #キリンホールディングス
- #セミナー
- #ノンアルコール飲料
- #早稲田大学
- #純アルコール量
- #適正飲酒
- #適正飲酒セミナー




















